試作で作っていたCROSSの残骸がフロッピーにありました。CROSSを考えて いたのはVOXを作る前、3年前でした。(ふ、古い〜(^^;) ついでなので、そのドキュメントCROSS.DOCから冒頭部分だけをここに引 用掲載します。(^^; CROSSの説明書というよりは「前後裁断」的というか「割り切る思考法」 (?)の説明みたいなものになっています。以前、自分勝手に酔って書いた ものなので、適当に読み流してください。 -------------- 引用ここから ------------ CROSS説明書 v1.00 ======================================================================== 【ソフト名】 CROSS v2.00 【著作権者】 START(垣添始) NIFTY-Serve GCA03416 【制作日付】 1996/03/19 【対応機種】 DOS汎用 【動作確認】 OASYS30-AX301 OASYS-Pocket3 PC-9801UV 【開発言語】 日本語プログラミング言語 Pure Mind PRO v5.2 基本セット ======================================================================== ●はじめに CROSSは、「どうしたら良いか分からない」と思えるあいまいな問題を、 ある基準で切っていく、つまり“大ナタを振るう”ことで、解決策を見い出して いくためのプログラムです。 また、そうしたテーマの「切り方」や「基準となる軸」の設定作業を通して、 自分なりの「価値観」や「人生観」を発見し、物事に対する判断力の向上を図る ことも大きな狙いとしています。 そのための有効な概念として、CROSSは情報データを「4象現」に分けて 取り扱う方法を取り入れています。 ここで言う「4象現」とは、適当な基準となるX軸とY軸を設定し、その2つ の軸が“クロス”してできた4つのポジションに、考えやアイディア、データな どを振り分け、物事を明確に整理しながら考えていくスタイルのことです。 私としては「人生について真正面から考えるプログラム」を目指したつもりで すが、あいまいな問題の解決から雑多な情報の整理まで、さまざまな使い方が考 えられると思います。 操作方法も、できるだけ直観的に分かるよう工夫してみましたので、気軽な思 考・整理ツールとして活用できるのではないかと期待しています。 ●割り切る思考法と実践 『前後裁断』という言葉があります。 一度、こんがらかってしまった糸は、いくら解(ほど)こうとしても、時間ば かりが掛かってしまい、簡単には解くことはできません。 そんな時は、心を決め、問題の「前後」をバッサリと「裁断」してから、糸を 結んでいかなければ、前へ先へと歩みを進めていくことはできません。 人生を生きていく上で、物事を実践に移していく上で、そうした「前後裁断」 の“割り切る思考法”は、煮詰まってしまった時の打開策を効果的に見いだす有 効な方法だと、私は思っています。 この世が、まるで矛盾に満ちた世界のように見える時があります。 もがいても、もがいても抜け出せない。同じところをぐるぐる回るばかりで、 出口を発見することができない。闇の方ばかりに目が行ってしまい、自分が沈ん でしまいそうになる・・・。 また、とてつもない怪物が、目の前に立ちはだかっているように思う時があり ます。自分の力では、とうてい打ち破ることのできない壁に出くわして、前に進 めない・・、と悲観に暮れる時もあります。 そんな時にこそ、CROSSの出番なのです。 執着することの愚かさを、生・老・病・死の四苦に分けて説いたり、因・縁・ 果・報の道理により、人の生き方や悟りをすすめた釈迦のように。 また、“十字”を切りながら、逆境の中で光を見い出し、二千年という時を生 き抜き続けてきた、偉大なるキリストの人々のように。 人生という糸が絡みそうになったら、一度、CROSSで自身の悩みを切り開 き、見つめ直してみてください。ひょっとしたら、目の鱗がポロリと取れ落ちて、 まったく新しいアイディアや、素晴らしい活路が見えてくるかも知れませんよ。 ●使い方の例 例えば、あなたが「職場の人間関係」を改善していきたいと思っているとしま す。しかし、人間関係というものは、抽象的な問題であり、主観がからむだけに、 なかなか良い改善策が見えてこないものです。 ◆STEP 1 そこで、次のように「立場」と「能力」という2つの尺度を用意すると、考える べき対象を明確にすることができ、改善策のヒントを探ることができます。
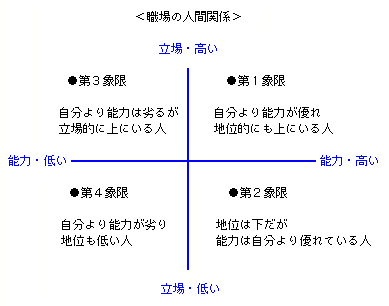 このように、まず、自分のまわりにいる職場の人々を、能力・立場という尺度
で4つの象限「クロス」に分けしてしまうのです。
「クロス」は、クラスと言っても良いのですが、クラスは差別的なイメージを
連想させるため、CROSSでは象限のエリアのことを「クロス」と呼びます。
すると・・・、
A.自分より有能な上司・・どうやってパイプを太くしていくのか?
B.自分より有能な部下・・どんな扱い方をすれば良いのか?
C.自分より無能な上司・・どんな態度をとっていくべきなのか?
D.自分より無能な部下・・どうな風に活かせば良いのか?
という具合に、あいまいだった問題が1レベル具体的な課題に変えることができ、
より具体的なレベルで考えを深めていくことができます。
ちなみに、同一の立場にある同僚も4クロスのどれかにとりあえず入れて、考えを
進めていくことを優先します。自分とまったく同じ人間はいないという判断です。
◆STEP 2
ここで、Bクロスの「自分より有能な部下」のことが気になるようなら、今度は
そのクロスに焦点を当てた「4クロス」を描いていきます。
その都度、自分なりの「4クロス」を描いていけば良いのですが、ここでは例と
して次のような「4クロス」を描き、より具体的な改善策のポイントを引き出して
みました。
このように、まず、自分のまわりにいる職場の人々を、能力・立場という尺度
で4つの象限「クロス」に分けしてしまうのです。
「クロス」は、クラスと言っても良いのですが、クラスは差別的なイメージを
連想させるため、CROSSでは象限のエリアのことを「クロス」と呼びます。
すると・・・、
A.自分より有能な上司・・どうやってパイプを太くしていくのか?
B.自分より有能な部下・・どんな扱い方をすれば良いのか?
C.自分より無能な上司・・どんな態度をとっていくべきなのか?
D.自分より無能な部下・・どうな風に活かせば良いのか?
という具合に、あいまいだった問題が1レベル具体的な課題に変えることができ、
より具体的なレベルで考えを深めていくことができます。
ちなみに、同一の立場にある同僚も4クロスのどれかにとりあえず入れて、考えを
進めていくことを優先します。自分とまったく同じ人間はいないという判断です。
◆STEP 2
ここで、Bクロスの「自分より有能な部下」のことが気になるようなら、今度は
そのクロスに焦点を当てた「4クロス」を描いていきます。
その都度、自分なりの「4クロス」を描いていけば良いのですが、ここでは例と
して次のような「4クロス」を描き、より具体的な改善策のポイントを引き出して
みました。
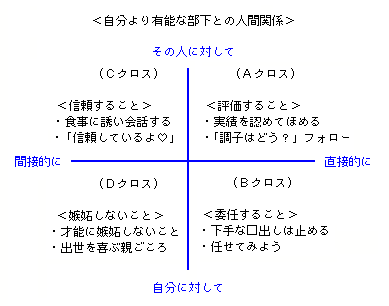 CROSSは、このような使い方をパソコン上でやったら面白いのじゃないか
ということで作ってみたプログラムです。
(私は象限学の専門家ではないので応用法はあなた自身で考えて下さいね)
●ファイル構造について
CROSSのファイルは、4象限のタイトルや2つの軸名を記録する Xファイル
と、各象限のデータを格納する A,B,C,Dファイルの2種類があります。
全体のタイトル・・・・Xファイル
X軸のタイトル・・・・ 〃
Y軸のタイトル・・・・ 〃
第1象限の内容・・・・Aファイル
第2象限の内容・・・・Bファイル
第3象限の内容・・・・Cファイル
第4象限の内容・・・・Dファイル
基本的に1象限1ファイル形式で構成され、どれもごく普通のテキストファイル
で良いため、エディターやファイラーなど、他のアプリケーションでも気軽にも修
正することが可能です。
CROSSの階層は、そのテキストファイルの名前(主ファイル名)の付け
方で秩序づけられており、各ファイルと階層の関係は次のようになっています。
説明を簡略にするために各階層で「A」だけを選択していった場合、「D」を選択し
続けていった場合の流れを表してみます。(拡張子名は省略)
CROSSは、このような使い方をパソコン上でやったら面白いのじゃないか
ということで作ってみたプログラムです。
(私は象限学の専門家ではないので応用法はあなた自身で考えて下さいね)
●ファイル構造について
CROSSのファイルは、4象限のタイトルや2つの軸名を記録する Xファイル
と、各象限のデータを格納する A,B,C,Dファイルの2種類があります。
全体のタイトル・・・・Xファイル
X軸のタイトル・・・・ 〃
Y軸のタイトル・・・・ 〃
第1象限の内容・・・・Aファイル
第2象限の内容・・・・Bファイル
第3象限の内容・・・・Cファイル
第4象限の内容・・・・Dファイル
基本的に1象限1ファイル形式で構成され、どれもごく普通のテキストファイル
で良いため、エディターやファイラーなど、他のアプリケーションでも気軽にも修
正することが可能です。
CROSSの階層は、そのテキストファイルの名前(主ファイル名)の付け
方で秩序づけられており、各ファイルと階層の関係は次のようになっています。
説明を簡略にするために各階層で「A」だけを選択していった場合、「D」を選択し
続けていった場合の流れを表してみます。(拡張子名は省略)
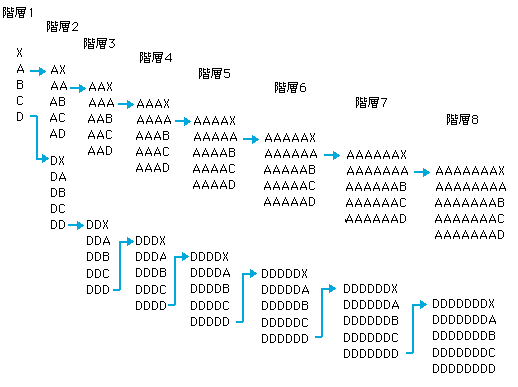 このように、X,A,B,C,Dというファイル名からスタートし、最深の階層では、
AAAAAAAX,AAAAAAAA〜DDDDDDDDというファイル名となります。
そのため、全階層にわたり全象限にデータを入力していくと、
最大で5×5×5×5×5×5×5×5=390,625ファイルを作り、扱うことができます。
●ファイル
-------------- ここまで引用 ------------
と、何だか難しく書いてますが、実際のところCROSSが役に立つのか立たな
いのか、本当のところは真剣に使い込んでいないのでまったく分かりません。
(^^;;
参考になれば幸いです。
実は、CROSSの他に、もうひとつ似たようなのを考えたことがあります。
(おいおいまだあるのかよ)こういうの好きなもんで・・・。(^^;;;
この書き込みの後にまたアップします。
このように、X,A,B,C,Dというファイル名からスタートし、最深の階層では、
AAAAAAAX,AAAAAAAA〜DDDDDDDDというファイル名となります。
そのため、全階層にわたり全象限にデータを入力していくと、
最大で5×5×5×5×5×5×5×5=390,625ファイルを作り、扱うことができます。
●ファイル
-------------- ここまで引用 ------------
と、何だか難しく書いてますが、実際のところCROSSが役に立つのか立たな
いのか、本当のところは真剣に使い込んでいないのでまったく分かりません。
(^^;;
参考になれば幸いです。
実は、CROSSの他に、もうひとつ似たようなのを考えたことがあります。
(おいおいまだあるのかよ)こういうの好きなもんで・・・。(^^;;;
この書き込みの後にまたアップします。